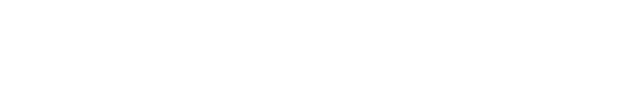パーキンソン病治療薬の種類
Lドパ製剤(ドパストン、メネシット、イーシー・ドパール、ネオドパストン、ドパコールなど)
高齢のパーキンソン病患者の第一選択薬です。純粋なパーキンソン病ではない、パーキンソン症候群に対してはこの薬剤のみ保険適応があります。
パーキンソン病は脳の中でドパミンという物質が少なくなることで起こります。であれば、ドパミンを補充してあげれば症状は改善するということです。では、ドパミンをそのまま内服すればパーキンソン病の症状は良くなるのでしょうか? 実は、それほど簡単ではありません。脳の神経は血液の中に存在するいろいろな物質によって影響を受けやすく、その影響を最小限にするために血管と神経の間には血液脳関門(BBB:Blood Brain Barrier)というフィルターが存在します。体の中で唯一脳にだけ存在する仕組みです。このおかげで脳は血液から余分な物は弾き、必要な栄養分だけもらうことができるのです。ですが、このフィルターのせいでドパミンも弾かれてしまいます。いくら頑張ってドパミンを内服しても、脳に到達させることは不可能なのです。ドパミンはもともと脳の中の神経で作られますので、血液の中からやってきてそれを利用するということは無いのです。
そこで登場するのが、このLドパという物質です。Lドパはドパミンの原材料みたいなものです。しかも都合のいいことにLドパであれば血液脳関門に弾かれることなく通過して脳に到達することができます。日本においては1972年、このLドパ単独製剤が初めて世に出回りました。それまでは抗コリン薬という間接的な作用での治療薬しかありませんでしたので、初の根本的な症状改善薬が誕生したということです。
しかし、このLドパ製剤には大きな欠点がありました。それは、Lドパはすぐにドパミンに変化してしまうという点です。血液脳関門を通過してからドパミンに変化してほしいのに、血液の中ですぐにドパミンに変化してしまうと、結局脳の中にはドパミンとして送り込めないということになります。必要なドパミン量を脳に到達させるためには大量のLドパを内服する必要があり、副作用などの問題がありました。そこで次に考え出されたのが、Lドパ→ドパミンへ変化させる酵素(脱炭素酵素)を働かなくさせる薬剤(脱炭素酵素阻害剤)です。これをLドパと一緒に服用すれば、血液の中ですぐにドパミンへ変化してしまうことを防ぎ、Lドパのままで血液脳関門を通過して脳内に到達、そして脳の中で脱炭素酵素によってドパミンに変化、ということが可能となりました。また都合のいいことに、この脱炭素酵素阻害剤は血液脳関門を通過することができませんので、脳内に入ってきたLドパがドパミンへ変化させることまで阻害するということはありません。このLドパ+脱炭素酵素阻害剤の配合剤はLドパ単剤の発売から遅れること8年、1980年に日本で発売開始となりました。
この配合剤の効果は素晴らしく、40年以上経った今でもパーキンソン病患者に対する内服薬のほぼ第一選択薬として位置づけられています。
ドパミンアゴニスト製剤(パーロデル、ペルマックス、カバサール、ビ・シフロール、ミラペックス、レキップ、ニュープロパッチ、ハルロピテープなど)
なんとか脳内にドパミンを届けようとして開発されたのが前述のLドパ製剤です。それに対して、このドパミンアゴニストとはドパミンの受け手(受容体)を直接刺激してしまおうという発想で開発された薬剤です。ドパミンは“神経伝達物質”という名前がついているのですが、その名の通り神経と神経の情報伝達を行う役割を持っています。電気活動という興奮を伝えたい側の神経はドパミンを放出し、受け手側の神経はそのドパミンを受容体と言われる部分でキャッチし、みずからが興奮します。ドパミンというなかなか脳内に届きにくい物質ではなく、簡単に脳内に届き、かつこの受け手側の神経の受容体にダイレクトにくっつく物質があれば、症状が改善するのでは?という発想です。アゴニストとは受容体に直接くっつく物質のことを言います。薬の世界では作動薬とも呼ばれています。
このドパミンアゴニスト製剤は比較的若いパーキンソン病の患者さんに対して、第一選択薬となります。症状改善の効果は前述のLドパ製剤より劣るのですが、Lドパと比べて症状の波が穏やかになることや1日1回の服薬で済むなどのメリットも多いです。ただし、昼間から眠気がでたり、ひどい場合だと突然前触れもなく寝入ってしまうという困った副作用が出る場合があります。ですので、車の運転はやめてもらうようお伝えしています。その他、長期間使用することで心不全や弁膜症という心臓のトラブルをきたすこともありますので、定期的なレントゲンやエコー検査が必要となります。
年齢や症状によって最初はLドパ製剤、ドパミンアゴニスト製剤のいずれか一方を選択するのですが、病勢の進行に応じで併用することが多くなります。併用するほうがお互いの量を減らすことが可能となり、ひいては副作用の出現を抑えることにつながります。
COMT阻害薬(コムタン、オンジェンティス)
Lドパ製剤の説明の中で登場した脱炭素酵素(Lドパ→ドパミンに変換する酵素です)以外にも、Lドパを分解する酵素が存在します。それがこのCOMT(catechol-O-methyl transferase)です。COMTによってLドパは3OMD(3-O-methydopa)という症状改善の観点からは役立たずの物質に変化してしまいます。役立たずの物質になるだけならまだしも、この3OMDはLドパより我先にと血液脳関門を通り抜けていきます。そのせいで、本来通り抜けてほしいLドパが後回しになってしまうのです。脱炭素酵素が普通に存在する中では、このCOMTの働きは目立たなく無視できていたのですが、脱炭素酵素阻害剤によって脱炭素酵素の働きをストップさせると、2番手としてこのCOMTによる影響が無視できなくなってきました。そこで、さらにCOMTの働きをストップする目的でCOMT阻害剤が開発され、2007年に初のCOMT阻害薬としてコムタンが登場しました。
また、Lドパに脱炭素酵素阻害剤、COMT阻害剤を追加した、とことんLドパを脳内に送り届けようというコンセプトのスタレボという薬剤も2014年に登場しています。
その他、2020年には1日1回の服用で済むオンジェンティスが世に登場しています。
MAO-B阻害薬(エフピー、アジレクト、エクフィナなど)
脳内のドパミンは前述したCOMTやMAO(monoamine oxidase)によって分解されます。
もし仮に脳内でこのCOMTやMAOの働きを抑えることができれば、分解されるドパミンが少なくなる、すなわち脳内のドパミン量が増えることになり、パーキンソン病の症状に対して有効なのではないか?という発想が生まれました。COMT阻害剤は残念ながら血液脳関門を通過することができませんが、このMAO阻害剤は容易に血液脳関門を通過できることがわかっています。MAOにはA型とB型の2種類があり、主にB型が脳内で多く存在し脳内のドパミンの分解に関与しているため、なるべく余計な他の影響を及ぼさないためB型のみ働きを抑えるMAO-B阻害薬が開発されました。この薬によって、約30%ドパミンの効果が高まると言われています。パーキンソン病は病状が進行してくるとドパミンの効きすぎ、効かなさすぎといった問題が出てくるのですが、このような症状の波に対してこのMAO-B阻害剤を追加することで、この波を緩やかにする効果が期待できます。
ただ、このMAO-B阻害剤には大きな問題点がありました。以前はエフピー(2007年発売)という薬のみ存在していたのですが、このエフピーはアンフェタミン骨格を有しており覚醒剤原料にもなるということで管理をしっかりする必要があったのです。患者さんやご家族の方が管理するぶんにはさほど問題にはならないのですが、施設へ入所する際などは手続きがややこしくなり、それを嫌がる施設もありました。
最近では1日1回の内服で済み、しかもこの覚醒剤の原料に当たらないアジレクト(2018年発売)、エクフィナ(2019年発売)という新しい内服薬が登場しています。
これらの薬の登場によって、我々処方する側にとっても随分と心理的ハードルが下がったように思います。
抗コリン薬(アキネトン、アーテン)
Lドパ製剤やドパミンアゴニスト製剤が世に出回る前はこの抗コリン薬のみがパーキンソン病の治療薬として用いられていました。
アセチルコリンという物質はドパミンと同じように脳内で神経伝達物質として働いています。このアセチルコリンという物質の作用を抑える働きのある薬を抗コリン薬と言います。
脳内ではドパミンとアセチルコリンはお互いに敵対関係(医学的には拮抗すると言います)にあるので、ドパミンが少なくなると相対的にアセチルコリンが優勢となり振戦(ふるえ)などの症状が出現してしまいます。ですので、ドパミンを増やすという方法以外に、敵対関係にあるアセチルコリンの働きを押さえれば症状が良くなるのでは?という発想から抗コリン薬が治療薬として用いられてきました。
確かに抗コリン薬を使用することで振戦は抑えられるのですが、抗コリン薬にはいろいろな困った副作用があります。
副作用の代表的なものとして喉の乾きや便秘というものがありますが、もともとパーキンソン病の患者さんはこのような症状があるため、さらに症状を悪化させてしまうことになります。また認知機能の低下もしばしば経験しますので、高齢患者さんにはあまり積極的には使いにくいということになります。また緑内障がある患者さんでは眼圧を上げてしまい、最悪失明の危険性もあるため使用することができません。
こういった理由で、比較的若い振戦が目立つパーキンソン病の患者さん以外、最近ではあまり使われなくなっています。また、その様な理由からなのかはっきりとはわかりませんが、アキネトンに関しては2023年に販売中止となってしまいました。アーテンに関しても今まで製造していた武田薬品が出荷を停止するなど、抗コリン薬の選択肢は徐々に少なくなってしまっているのが現状です。
ゾニサミド(トレリーフ、エクセグラン)
トレリーフ、エクセグラン、ゾニサミドという内服薬は、全てゾニサミドという薬物ですので、中身は同じです。(値段は大きく違いますが、ここではその理由などは割愛します。)もともとてんかんの発作を抑える薬として開発されました。
神経が僅かな電気刺激を受けた際、T型カルシウムチャネルというカルシウムイオンだけを通すゲートが開き大きな電気活動になって刺激が別の神経へ伝わっていきます。特定のイオンだけを通すゲートは他にもいくつか種類があるのですが、睡眠障害や痛み、てんかん、振戦、運動緩慢にはこのT型カルシウムチャネルが必要以上に興奮することで起こっている可能性が示唆されています。ゾニサミドはこのT型カルシウムチャネルの興奮を抑える作用があり、その結果パーキンソン病の症状でもある振戦、動作緩慢に対して効果を発揮します。
また、ゾニサミドにははっきりとした作用機序はわかっていませんが、ドパミンをより多く合成させることができるようです。さらに、ドパミン神経細胞自体が死んでいくのを抑える作用、すなわちドパミン神経の保護作用も有していることが分かってきました。
Lドパ製剤やドパミンアゴニスト製剤と比べると薬の切れ味は一歩劣りますが、ドパミン神経保護作用に関しては他の薬剤には無い特徴です。てんかんの場合には1日に300mg程度処方するのですが、パーキンソン病の場合はわずか25mg程度でも振戦や動作緩慢に対して効果を発揮します。また50mg程度に増量すればLドパ製剤やドパミンアゴニスト製剤を使用しているときに見られる症状の波を穏やかにしてくれる作用も期待できます。
普段てんかんも診ている脳神経外科医にとっては馴染みも深く大変使いやすい薬剤の印象があります。
アマンタジン(シンメトレル)
アマンタジンはもともとA型インフルエンザに対する治療薬として開発されました。
その後、パーキンソン病の患者さんがアマンタジンをたまたま内服したところ著しい症状改善を認めたため、当初の薬効とは全く別の薬効も追加承認されたという歴史があります。
後になってから、アマンタジンには神経細胞内でドパミンの合成を促進させ、さらにはドパミンの放出を促進させる効果があることがわかりました。
また、アマンタジンは誤嚥性肺炎を防ぐ目的で処方されることもあります。(保険外適応ですが。)咳反射に重要な役割を持っているドパミン及びサブスタンスPを増やす働きがアマンタジンにはあるようです。ある程度病状が進んだパーキンソン病患者さんにとって誤嚥性肺炎は命を脅かす重大なリスクとなりますので、そういった患者さんには積極的に使用することもあります。
さらには、アマンタジンにはノルアドレナリンやセロトニンといった神経伝達物質にも影響を及ぼすことが分かっています。気持ちを前向きにさせる効果があり、脳梗塞後遺症や認知症の患者さんで意欲が低下してしまった場合に有効です。パーキンソン病の患者さんも病状が進むに連れ意欲低下、無気力、うつ状態になるケースも多く、このような場合にも積極的に使用することがあります。
ドロキシドパ(ドプス)
ノルアドレナリンという物質があります。交感神経に作用する物質ですが、大きな働きの一つに血圧を上げるというのがあります。また、脳内では神経伝達物質としても働き、恐怖や怒り、不安、集中、覚醒、鎮痛などに関与しています。ノルアドレナリンは通常ドパミンを原料として作られるのですが、パーキンソン病の患者さんの脳内ではドパミンが元々減っていますので、それによって作られるノルアドレナリンの量も減ってしまっています。そのことが原因となり、すくみ足(最初の一歩が出にくい)や起立性低血圧(急に立ちくらみがして倒れてしまう)がパーキンソン病の患者さんでは見られやすいです。では、このような症状に対して足りないノルアドレナリンを投与すればいいのではと考えますが、またここで前述した血液脳関門というフィルターが立ちはだかります。ドパミンと同じようにノルアドレナリンもこのフィルターを通過することができません。いくらノルアドレナリンを投与しても、脳内まで届けることはできないのです。(それどころか、体中の交感神経が異常に興奮して大変なことになってしまいます。)ここで考え出されたのが、本来体の中には存在しない別のノルアドレナリンの原料となる物質:ドロキシドパでした。このドロキシドパは血液脳関門を通過することができ、またLドパをドパミンに変換する脱炭素酵素によってノルアドレナリンへと変化します。
ノルアドレナリンはそれ自体も、その原料となるドパミンもどちらも血液脳関門を通り抜けることができませんが、元来体の中には存在しない別の原料を開発することで脳内に届けることが可能となり、パーキンソン病の症状のうち起立性低血圧やすくみ足に対して有効な治療薬となりうることになったのです。
アデノシンA2A受容体拮抗薬(ノウリアスト)
大脳基底核という部分に存在する神経細胞のドパミンが減少すると、その部分ではアデノシンという物質が優位となり、GABAという物質が必要以上に作られます。GABAは気持ちを落ち着かせたり、体の動きを抑えたりする効果がある神経伝達物質です。パーキンソン病の症状の一つに体の動きにくさというのがありますが、その原因の一つにこのGABAという物質が関係しています。
ですので、このGABAという物質を必要以上に作らせない目的で、アデノシンがくっつく受容体自体の働きを抑えてしまうアデノシンA2A受容体拮抗薬が開発されました。
この薬は主にLドパ製剤を長期間にわたり服用し、病状の悪化とともに症状の波が強くなってきた患者さんに対して使用します。急に薬の効果が切れるのを防ぐ目的です。
少し余談にはなりますが、コーヒーの中に含まれるカフェインもこのアデノシンA2A受容体の働きを抑える作用があります。ですので、コーヒーを飲むと気持ちを落ちつかす作用のあるGABAが少なくなることで眠気が取れる、もしくはよる寝付きが悪くなるといった現象が現れます。
パーキンソン病の治療薬には急に眠気を及ぼすという副作用を持つものが多いですが、このアデノシンA2A受容体拮抗薬はカフェインと同じように覚醒作用がありますので、こういった作用もうまく利用することで普段の生活の質を上げることも可能となります。